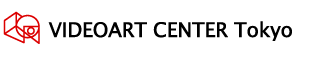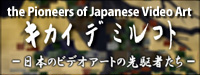「インディペンデントなアーティストのネットワーク」瀧健太郎[その2]
[ネットワークを通じて]
各グループとのコラボレーションはEメールなどのやりとりを中心に、往々にして円滑にゆき、話し合いの結果それぞれの都市で少しずつ内容の違うイベントを行うことができた。ジャカルタでは、ビデオアート自体がまだそれほど浸透していない表現方法であることもあり、個々の作品の技術的なことへの関心を感じ、また彼らは都市のイメージに非常に興味があるようだった。
各グループとのコラボレーションはEメールなどのやりとりを中心に、往々にして円滑にゆき、話し合いの結果それぞれの都市で少しずつ内容の違うイベントを行うことができた。ジャカルタでは、ビデオアート自体がまだそれほど浸透していない表現方法であることもあり、個々の作品の技術的なことへの関心を感じ、また彼らは都市のイメージに非常に興味があるようだった。
ジュネーヴでは映像の制作する環境、アートを作り続ける環境としてインディペンデントなグループを作ることはもちろん前提としてあり、それ以上に非常に行政と関わっている印象を受けた。更にどの作家も国際的感覚にすぐれ、フットワークの軽さを見て取れた。ベルリンではもっと社会的な問題と制作の関連、アーティストによる自治の問題や、いわゆる現代美術の分野とビデオアートの距離を測ることができた。
香港ではインスタレーション展示を行ったこともあり、ビデオのオブジェとしての可能性を提示することができ、そのことが非常に有効であった。パリでは映画発祥の地であることからか、観客も作家もビデオよりフィルムへの依存があることを知ることができた。
ジュネーヴ展にて
結果巡回展では、EU型のアートをアジアに伝えることや、逆に起こりつつあるアジアのオルタナティヴなアートの状況をEUで紹介するという情報の交換を中心に、映像、アートのみならずメインカルチャーにむけてサブカルチャーの提示を、マスメディアに対して単なるパーソナルなメディアを提示するのではなく、結束されるべきアクティヴィティーの認識を、同様に世界のグローバル化に対抗し、ローカル化を安易に打ち出すのではなく、芸術やその運動から可能性を提案することの重要性を、各都市の展覧会を通じて再考し、準備する事となった。今後同様に巡回展だけを繰り返すということは計画されていないが、作家間のあるいはアーティスト・グループ間のやり取りは耐えることなく、新しいプロジェクトが計画され続けるだろう。

Ade Darmawan(Indonesia)
[アーティスト達に逢う -1-]
巡回展を行うにあたって同時に進行した企画は、現地に趣いたときに、そこでのアーティスト・グループやテレピデミク!参加作家のインタビューを試みるということであった。インドネシアでは中村明子と共にRuangrupaルアングルッパの主催者に組織の立ち上げから、ジャカルタ初のビデオ・フェスティバルを催すに至るまでの、様々な困難や運営の苦労などを聞くことができた。(インドネシアでのインタビュー詳細は別途記載予定。)筆者はジュネーヴでウルリッヒ・フィッシャーと、ドイツではハーラルト・ブッシュとニコラス・ジーペン、タラ・ヘルプスト、香港ではノーズ・チャン、東京で河合政之、印牧和美、西山修平、中村明子、服部かつゆき、フランスではマルク・プラスとユーゴ・ヴェルランドと、ほとんどのテレピデミク!参加作家のインタビューを行った。(インタビューの詳細はインタビューとして公開予定。)
 Ulrich Fischer(Switzerland)
Ulrich Fischer(Switzerland)
ウルリッヒ・フィッシャーは彼が関わったコミナール・キノ(自治映画館)「cinema sputnik」やフィルム現像ラボ「ゼブラ・ラボ」、そして昨今彼が中心に関わっている「perceuse」などについて話してくれた。 また作品に関しては、「加速可能」(1998)が当時興味あったポール・ヴィリリオの考えを受けて、加速する世界を映像の断片で表現することに端を発して制作したと教えてくれた。
ヴィリリオは現代社会の合理化の影の部分に飽くことなく批判を展開してきたフランスの哲学者である。同様に彼のどの作品もいろんな意味で断片(fragments)によって構成されていること、つまりそれは、映像表現においては雄弁な語り部にはなれない(それを行うと観客を無理にある一定の方向へ仕向けることになるため。)ことを知っており、そのために様々な断片を与えることで想像できる部分の余地を残しているのだと言える。
 Harald Busch(Germany)
Harald Busch(Germany)
ハーラルト・ブッシュとは彼の拠点ブレーメンで会ったあと、アシャッフェンブルグという小さな街で行われたグループ展で作品を見ることができた。彼は80年代からビデオと彫刻に取り組み、映画制作も試みて一時はフィルムも手掛けたが、即時性に欠けることからビデオを表現手段として選び、またビデオ・フェスティバルなどで他の作家が映像をやたらと(映画のように)大きく投影したがったことに少々失望させられ、ビデオをモニタで扱うことを決めたという。
「アートの領域でビデオを扱うことの一つの特徴はそれが既にどこにでもあるということです。また以前に彫刻を学んでいたこともあり、ビデオを映画の視点から見るのではなく、彫刻の視点から見ることで彫刻として扱うことが容易にできました。」彼はテレビモニタを物=オブジェとして扱う方法に興味があり、それが持ち運びが可能で、プラグさえ繋がればどこにでも設置できるという有用さに可能性を見出している。
彼のビデオ作品もビデオ彫刻作品においても、ある一定の客観性を見出すことができるのはそのためであろう。映像で示される内容よりも、それを見せている環境が我々に伝わってくる。 [つづきへ]
香港ではインスタレーション展示を行ったこともあり、ビデオのオブジェとしての可能性を提示することができ、そのことが非常に有効であった。パリでは映画発祥の地であることからか、観客も作家もビデオよりフィルムへの依存があることを知ることができた。
ジュネーヴ展にて
結果巡回展では、EU型のアートをアジアに伝えることや、逆に起こりつつあるアジアのオルタナティヴなアートの状況をEUで紹介するという情報の交換を中心に、映像、アートのみならずメインカルチャーにむけてサブカルチャーの提示を、マスメディアに対して単なるパーソナルなメディアを提示するのではなく、結束されるべきアクティヴィティーの認識を、同様に世界のグローバル化に対抗し、ローカル化を安易に打ち出すのではなく、芸術やその運動から可能性を提案することの重要性を、各都市の展覧会を通じて再考し、準備する事となった。今後同様に巡回展だけを繰り返すということは計画されていないが、作家間のあるいはアーティスト・グループ間のやり取りは耐えることなく、新しいプロジェクトが計画され続けるだろう。

Ade Darmawan(Indonesia)
[アーティスト達に逢う -1-]
巡回展を行うにあたって同時に進行した企画は、現地に趣いたときに、そこでのアーティスト・グループやテレピデミク!参加作家のインタビューを試みるということであった。インドネシアでは中村明子と共にRuangrupaルアングルッパの主催者に組織の立ち上げから、ジャカルタ初のビデオ・フェスティバルを催すに至るまでの、様々な困難や運営の苦労などを聞くことができた。(インドネシアでのインタビュー詳細は別途記載予定。)筆者はジュネーヴでウルリッヒ・フィッシャーと、ドイツではハーラルト・ブッシュとニコラス・ジーペン、タラ・ヘルプスト、香港ではノーズ・チャン、東京で河合政之、印牧和美、西山修平、中村明子、服部かつゆき、フランスではマルク・プラスとユーゴ・ヴェルランドと、ほとんどのテレピデミク!参加作家のインタビューを行った。(インタビューの詳細はインタビューとして公開予定。)
 Ulrich Fischer(Switzerland)
Ulrich Fischer(Switzerland)ウルリッヒ・フィッシャーは彼が関わったコミナール・キノ(自治映画館)「cinema sputnik」やフィルム現像ラボ「ゼブラ・ラボ」、そして昨今彼が中心に関わっている「perceuse」などについて話してくれた。 また作品に関しては、「加速可能」(1998)が当時興味あったポール・ヴィリリオの考えを受けて、加速する世界を映像の断片で表現することに端を発して制作したと教えてくれた。
ヴィリリオは現代社会の合理化の影の部分に飽くことなく批判を展開してきたフランスの哲学者である。同様に彼のどの作品もいろんな意味で断片(fragments)によって構成されていること、つまりそれは、映像表現においては雄弁な語り部にはなれない(それを行うと観客を無理にある一定の方向へ仕向けることになるため。)ことを知っており、そのために様々な断片を与えることで想像できる部分の余地を残しているのだと言える。
 Harald Busch(Germany)
Harald Busch(Germany)ハーラルト・ブッシュとは彼の拠点ブレーメンで会ったあと、アシャッフェンブルグという小さな街で行われたグループ展で作品を見ることができた。彼は80年代からビデオと彫刻に取り組み、映画制作も試みて一時はフィルムも手掛けたが、即時性に欠けることからビデオを表現手段として選び、またビデオ・フェスティバルなどで他の作家が映像をやたらと(映画のように)大きく投影したがったことに少々失望させられ、ビデオをモニタで扱うことを決めたという。
「アートの領域でビデオを扱うことの一つの特徴はそれが既にどこにでもあるということです。また以前に彫刻を学んでいたこともあり、ビデオを映画の視点から見るのではなく、彫刻の視点から見ることで彫刻として扱うことが容易にできました。」彼はテレビモニタを物=オブジェとして扱う方法に興味があり、それが持ち運びが可能で、プラグさえ繋がればどこにでも設置できるという有用さに可能性を見出している。
彼のビデオ作品もビデオ彫刻作品においても、ある一定の客観性を見出すことができるのはそのためであろう。映像で示される内容よりも、それを見せている環境が我々に伝わってくる。 [つづきへ]