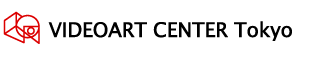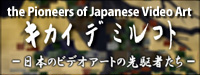カテゴリ:Video ARTicle
松本俊夫 時代の碑から構造の問題へ<その2>
映像作家 松本俊夫 時代の碑から構造の問題へ
 「コネクション」(1981)
「コネクション」(1981)
未公開作品「Hands」 (1977) 、「Double」 (1977) をバックグラウンドで上映したのち、後半には「コネクション」 (1981) 、「リレーション 関係」 (1982 年 ) 、「シフト 断層」 (1982) が上映されました。 後半は会場の観客からの質疑が行われました。
---------------------------------------
音と映像のコラボレーションについて
質問:一柳慧さんや稲垣洋祐さんなどが音を担当されていますが、作品に音をつける際にどういう意識を持っていらっしゃいますか?またはコラボレートする音楽家に一任されるのでしょうか?
松本:もちろんいろいろ話をします。作品がどういう世界を狙っているか、その意図とそれを作品として構築してゆく上でのポイントがありますが、そのあたりを際立たせるために全体というのが組み合わされているわけです。といってもやはりそれを一つにするに当たって対立させたり、融合させたりというのか、そういう関係なので、音と映像、聴覚と視覚の関係というのは、作品によっては、かなりぶつかり合うようにしようとか、あるいは溶け合うようにしようとか、あるいは構造的にここまではこう、といったことが大きく打ち合わせられます。
撮影の場合もそうですが、映像のコラボレーションというのは、作品を積み重ねる中でお互いがだんだん分かってくるというか、自分の作品以外のことでも、いろいろな考え方や趣味の交流があるし、そんなことを含めつーかーになってゆくのですね。それと信用しあうところと、だからこそ分かり合う範囲内のことだけをやるわけにもいかない、相手にハッとさせるような何かをぶちかましてやろう、ということも出てくるわけです。言ってみれば刺激的なインタラクションが起きるわけで、その楽しみで創っているわけです。
その2
 「コネクション」(1981)
「コネクション」(1981)
未公開作品「Hands」 (1977) 、「Double」 (1977) をバックグラウンドで上映したのち、後半には「コネクション」 (1981) 、「リレーション 関係」 (1982 年 ) 、「シフト 断層」 (1982) が上映されました。 後半は会場の観客からの質疑が行われました。
---------------------------------------
音と映像のコラボレーションについて
質問:一柳慧さんや稲垣洋祐さんなどが音を担当されていますが、作品に音をつける際にどういう意識を持っていらっしゃいますか?またはコラボレートする音楽家に一任されるのでしょうか?
松本:もちろんいろいろ話をします。作品がどういう世界を狙っているか、その意図とそれを作品として構築してゆく上でのポイントがありますが、そのあたりを際立たせるために全体というのが組み合わされているわけです。といってもやはりそれを一つにするに当たって対立させたり、融合させたりというのか、そういう関係なので、音と映像、聴覚と視覚の関係というのは、作品によっては、かなりぶつかり合うようにしようとか、あるいは溶け合うようにしようとか、あるいは構造的にここまではこう、といったことが大きく打ち合わせられます。
撮影の場合もそうですが、映像のコラボレーションというのは、作品を積み重ねる中でお互いがだんだん分かってくるというか、自分の作品以外のことでも、いろいろな考え方や趣味の交流があるし、そんなことを含めつーかーになってゆくのですね。それと信用しあうところと、だからこそ分かり合う範囲内のことだけをやるわけにもいかない、相手にハッとさせるような何かをぶちかましてやろう、ということも出てくるわけです。言ってみれば刺激的なインタラクションが起きるわけで、その楽しみで創っているわけです。
70年万博とアヴァンギャルド作家の立場
質問:なぜ大阪万博(*)に出品したのですか?
松本:一番大きな理由は、万博が非常にスケールの大きいインターメディアだからですね。直径15mか20mぐらいのドームを作っ て、そのドームにレリーフ状の彫像をいっぱい作ってストロボ状に周囲を動かし、壁から天井まで含めた環境を作って、そこに映像がいろんな形で映るわけで す。
その彫像っていうのは横尾(忠則)君に担当してもらった部分なのですが、僕が映像で撮った唯一の被写体っていうのは一人のバレエを踊る女の子なんです。そ の女の子を直接、今度はそこから型をとって、その型をとった同じ映像、片方は映像、片方は彫刻にして壁にストロボ彫刻的に配置して映るものは、その女の子 がそこに彫像の上にも映れば、ひっかかっている脇にも映るという、-口では説明しずらいのですが-、いろんな仕掛けを含めた18台のプロジェクターによっ てそれらが、像と彫刻といったようなつまり実像と虚像が交じり合うわけです。一方で舞台照明的な照明がたくさん付いていまして、それが彫像を照明すること で彫像がフワッと浮かび上がってくる映像との関係が生まれるといったような非常に複雑な展開をするのです。
そういうインターメディアといったような、その意味でまったく新しい試みだったのです。インターメディアの一番本質的なところは、従来のジャンルというの が整然とあって、そのジャンルの垣根をもかき回しているわけです。名付けようもない、ある種の体験を生み出す、と。「そんなものは芸術じゃない」と言われ れば、「それは芸術じゃなくても結構です」と言って。それは何らかのとても強い体験を生み出し、そこにある種の価値を見出すという視点の変化を求めている ので、芸術でないっていうなら芸術でなくてもかまわないし、そういう意味で、既成のある種の境界線を全部かき回して、新しいものを生み出そうとしているわ けです。
そういうことは当然ながらお金が掛かり、やはり個人ではそれは出来ないわけです。もちろん僕にはまったく個人の作品もあります。中では一人で作っているよ うな、すべてカメラから音から全部一人で作っているというのもあるし、万博なんかの場合にはそれは物凄くスケールが大きくなるわけです。その場合、建物も そういうものをやる為の建物を建てていますから、とても個人で出来るレベルのものではない。そういうビッグアーツというか、そういうこと自体の体験という のをやはりその時代にやってみたい、というところはあった。それが一番大きい理由です。
(*)大阪万国博覧会EXPO'70にて松本俊夫は「せんい館」の総合プロデュースを担当する。
横尾忠則の他、秋山邦晴、今井直次、湯浅譲二、吉村益信、四谷シモンなどが参加。松本は「スペース・プロジェクション・アコ」を出品。
質問:そのプランが実現できるから出品したのでしょうか。西洋近代のパラダイムを問うという意味では前年の69年の京大をピークにして反万博という形で動いていた人達もいたわけですよね。
松本: それはプラス・マイナスいろんな相反する要因を孕んでいて、とても悩みました。政治的な要因でいえば万博というのはやはり国家と結びついているし、もちろ ん国家的なイベントというものの本質を見ていなかったのではないわけで、それはすごく悩んだところではあります。だけども、結局プラス・マイナスの置き換 えのきかないプラス面をやはりここではどうしてもやっておきたいと思ったのです。
もしもやらなかったら多分、「薔薇の葬列」もできなかった。つまりそういうものが、資金になったのです。「薔薇の葬列」なんかでもATGと監督とが半々出 し合って作ったものがATGのアート・シアターのようなものでした。僕も若くて本当に貧乏だったので、そういう資金をつくることも出来なかったのです。簡 単に言えば、万博をやることの中でのギャランティーを、今度はアート・シアターで作る作品の資金源にするといったようなことで、それをまた可能にしてい く。それがさらに次の可能性へと繋がっているというふうに考えれば、やった場合とやらない場合でやっぱりずいぶん違っただろうと。やらなかったら僕の創作 活動はどうなっていたか、恐らくまるで違うものだったと思います。
そういうこともあって、結局は片方を選択しているわけだから、もう片方との関係でどうなったかというのは想像する以外にないですね。
質問:松本さんの作品を通じて、これからの社会を予見したいというような意思を感じました。
松本: 近代というものの行き詰りというものをすごくやっぱり60年代後半から感じるようになって、大げさに言えば人類の文化のありかたに係わるわけです。長い時 間、僕らのライフスタイル、ものの考え方、感じ方、それから価値観、いろんなものを一つの枠組みとして作っているその中でその枠組みの息苦しさをなんとか 変えなきゃいけない。もちろん近代というのは馬鹿にできないわけで、ものすごく大きい足跡を人類の文化に残しているし、ものすごく大きな問題提起もあった し、簡単に否定できるようなものではありませんが、少なくともやっぱり60年代の後半になってくるとその行き詰まりが、いろんな形で出始めていたことは事 実です。
その時代には、近視眼的にいうと70年安保があっただけに、70年安保が決戦であるといったような考え方にみんながなりがちでしたが、―僕はそれも軽視す るわけではないけれども―、僕はもっと射程を大きく捕らえるというか、70年安保といったような射程ではなくて、近代というものをどう超えていくかという ことを、創作の中にあるいは芸術思想の中に孕んでないようでは駄目だと思っています。その追求みたいなものが基調音になっているというのかな、そういう意 味では作家っていうのはみんな少しずつ共通した点もあれば違う面もありますね。
近代の超克と構造主義的アプローチ
質問:超克の仕方というのはどういうことなのでしょうか?
松本:それを一口でいうのは難しいですね、大問題ですから。だからそれは恐らく僕自身は、さっき半世紀って笑い話に出ましたが、実際半世紀かかっているわけで、未だ追求中です。でも時代としてかなり、みんなそういうことを考えるようになってきたのは事実ですね。
質問: 80年代の作品「シフト」はエフェクトを多様されているのですが、それほど難しいエフェクトではないのですが、構成自体が面白くユーモアがあると思いまし た。これは構造主義として捕らえることができると思いますが、シンプルなエフェクトを使っている「シフト」についてのお考えをお願いします。
松本:「シフト」はある意味では追求したことが、よく見える作品かと思います。画面をいつも層にスライスしていますよね。実際の被写体は建物の空間だけで、何も動いているものが一つもないわけです、人も出てこないし。
 「リレーション 関係」(1982)
「リレーション 関係」(1982)
撮ったときの素材として動いているのはカメラだけなのです。それを素材にしながら、6層に層をスライスして、その層のお互いのそれぞれのイメージの関係を 時間的にずらしていっているわけです。例えばカメラがずぅーっとパンをした、そうすると上から一段おきに1、2、3、それから戻って4、5、6、というふ うに何分の一秒かをずらして、次々にパンが始まると。そうすると時間のズレが相当な空間の歪みを作っていくわけです。空間のネジレみたいなものを作ってい く。その時間と空間の関係に目を向けているわけですね。
要するに、時間のずれが空間の歪みを作りながら、空間のイメージ全体が思ってもないようなものに変わっていく。あるいは、建物というイメージ自体が最初 の本当の建物はどんな建物だったのだろうとわからなくなるくらい複雑に変容していきますよね。その在り方が、その6つの要素の時間のずれの組み換えをやっ ているわけです。組み換えをやることでイメージがガラっと変わっていく。これは僕が勝手にそう思っているのかも知れませんが、この組み換えというのは、言 語学者ソシュールの晩年の「アナグラムの研究」というのがあり、-アナグラムの研究というのは詩的言語の研究ですが-それで言葉の置き換えをやるわけで す。アナグラムというのは、西洋のアルファベットを扱う言葉の人達は、単語などを一つ一つ切り離して、それを置き換えるわけですね。すると全然別の意味の 単語に変わってしまったりする。そういう遊びがあって、ゴダールなんかはしきりにそのアナグラムを映画の中に持ち込んでいます。
それを単語の個々の単語の単位じゃなくて、もうちょっとイメージの単位で置き換えをやっていったときに、これはイメージがアナグラムみたいに、若干似た関 係で生まれてくる。そのアナグラムの在り方の中に、時空間の解体と再構成といったようなことが生まれて、ものを生み出していくときの原理がそこに体現して ゆき、それが構造的であると、こだわっていたのです。構造そのものというよりは構造化なのです。構造化というプロセスとそのメカニズムそのものを見ていく というような作品だったのです。
それで、建物はある意味では仮の素材としてそういうものが現れやすい建物を選んだということなのですが、偶然かどうか分からないけれどこの年にたまたま 日本建築学会100年記念の学会が開かれて、その学会の大会でこれを上映させてくれと言ってきたのです。
建物自体は別に建築学会で今、大騒ぎするような建物ではないわけで、何を考えているのかと思ったのですが、後で聞いてみると、やはり建築の設計原理とし ていろんな建築上の要素、構造的な要素の単位をいろんな形で組み替えていると。
ユニットとしての構造の組み替えを通して、建築の設計をどんどん展開していくといったような発想を刺激するのでお借りしたんだということで、やっぱり共通しているなと思いました。
瀬島:建築学会100周年のときの相談がきたときに映像で何か、建築学会と映像の接点で何かイベントをやりたいという相談がありました。それで、どういう作品がいいのか、インスタレーションにするのがいいのか。
松本:82年ですね、これは。
瀬島: そこで、いろいろ考え、私としてはこの「シフト」がぴったりではないかなと思いました。たまたまこの建築学会が大成建設の銀座のビルかどこかでやっていた だいたのですが、この構造がみえてくる映像作品「シフト」と、もう一方にモニターを置いてアメリカのビル群をダイナマイトで爆破して壊していくっていう景 色が延々と流され、それと時折磯崎新さんがレクチャーしている映像との、全部で3つの映像を並べ、ある種一つ一つの構造が組み上がっていくことをやりまし た。インスタレーションとしてはそんなに思ったようなことは出来なかったのですが、やっぱりこの「シフト」という作品がある意味でその頃のデコンストラク ションをかなり考えていた建築家たちには非常に好意を持って見てもらえ、かなりの建築家たちに見て頂いたと思いますね。
松本:それと偶然の一致なんだけれど も、国際建築学会っていうのがボルドー辺りにあって、そこからも言ってきて、それはパリのポンピドゥー・センターでのビデオアートのプログラムがあって、 そこで作品を見た人が「あれを貸してほしい」と言ってきたことがありました。日本の建築学会に言われてそうなったのか、僕は知りませんけれどもそういう意 味では偶然に半年ぐらいの時間差をおいて、そういうことがありましたね。
それからもう一つ、ちょっといわゆるエフェクトをかなり使っているっていうのは、確かにこういう処理っていうのはデジタルな編集システムが初めて入ってき た頃で、-80年代の頭ですから、まだたいしたことは出来ないのですが-そういう試みも含めて、ある段階までは僕はテクノロジーがもたらす芸術方面の可能 性っていうことを、いつも割と大きい要因としてあったのです。
しかし、その後にものすごくそういう装置が増えましてエフェクターみたいなのが増えて猫も杓子も、そういうエフェクトシンドロームみたいな状態が出てきま した。それが逆にすごくそれぞれの作家の固有なこだわり方を曖昧にさせてしまって、似たり寄ったりになってしまいました。
ということがとても気になって、僕は80年代の半ばになると、逆にそういうエフェクトを含めて、幻視的な特殊技術みたいなものをできるだけ使わないという 方向に切り替えて、それが良いというのではなくて、要するに日本全体で起きている流れに一つの疑問を提起するというところがありました。
それからまた、その頃に課題として、-今言ったような時空間のねじれみたいな脱構築みたいな話がでましたけれども-デコンストラクションをもうちょっと人 間がものを意味づけるときの在り方を物語性として捉えると物語の次元ですごく型にはまったようにしか物を見ていない、意味付けをしていない、その辺りの問 題に踏み込んでいく、そこを脱構築する、という方向に向かってですね、意味をぐらつかせるっていう文脈の脱構築の方向に焦点を変えていったのですね。
それは、88年には劇映画で「ドグラマグラ」という作品を作りました。ご覧になった方は、あるいは「ああなるほどそういうつながりでか」とお分かりになる かと思いますが、そういう展開がそのあたりでは、80年代の後半には別な展開へと変わっていってるわけですね。
司会:本日はどうもありがとうございました。
その1へ
---------------------------------------
2001年から2005年のファイドロス・カフェのビデオアート・ショーイングは今回が最終回となり、カフェも4月に閉店することになっており、上映会終了後、瀬島久美子さんからカフェのオーナーの戸田久美子さんに花束が渡されました。
2001年に若手ビデオ作家の邂逅の場として、また一般のお客に気軽に映像作品を見てもらおうというアイデアから戸田久美子さんとビデオアーティスト河合 政之氏がオープンしたファイドロス・カフェでしたが、3年間様々なゲストやアーティストを迎えて渋谷に一つの映像文化の拠点を作り上げました。この松本俊 夫さんと瀬島久美子さんのゲストを迎えてのファイドロス・カフェのビデオアート・ショーイングが最終回となりました。3年間本当にありがとうございまし た。
質問:なぜ大阪万博(*)に出品したのですか?
松本:一番大きな理由は、万博が非常にスケールの大きいインターメディアだからですね。直径15mか20mぐらいのドームを作っ て、そのドームにレリーフ状の彫像をいっぱい作ってストロボ状に周囲を動かし、壁から天井まで含めた環境を作って、そこに映像がいろんな形で映るわけで す。
その彫像っていうのは横尾(忠則)君に担当してもらった部分なのですが、僕が映像で撮った唯一の被写体っていうのは一人のバレエを踊る女の子なんです。そ の女の子を直接、今度はそこから型をとって、その型をとった同じ映像、片方は映像、片方は彫刻にして壁にストロボ彫刻的に配置して映るものは、その女の子 がそこに彫像の上にも映れば、ひっかかっている脇にも映るという、-口では説明しずらいのですが-、いろんな仕掛けを含めた18台のプロジェクターによっ てそれらが、像と彫刻といったようなつまり実像と虚像が交じり合うわけです。一方で舞台照明的な照明がたくさん付いていまして、それが彫像を照明すること で彫像がフワッと浮かび上がってくる映像との関係が生まれるといったような非常に複雑な展開をするのです。
そういうインターメディアといったような、その意味でまったく新しい試みだったのです。インターメディアの一番本質的なところは、従来のジャンルというの が整然とあって、そのジャンルの垣根をもかき回しているわけです。名付けようもない、ある種の体験を生み出す、と。「そんなものは芸術じゃない」と言われ れば、「それは芸術じゃなくても結構です」と言って。それは何らかのとても強い体験を生み出し、そこにある種の価値を見出すという視点の変化を求めている ので、芸術でないっていうなら芸術でなくてもかまわないし、そういう意味で、既成のある種の境界線を全部かき回して、新しいものを生み出そうとしているわ けです。
そういうことは当然ながらお金が掛かり、やはり個人ではそれは出来ないわけです。もちろん僕にはまったく個人の作品もあります。中では一人で作っているよ うな、すべてカメラから音から全部一人で作っているというのもあるし、万博なんかの場合にはそれは物凄くスケールが大きくなるわけです。その場合、建物も そういうものをやる為の建物を建てていますから、とても個人で出来るレベルのものではない。そういうビッグアーツというか、そういうこと自体の体験という のをやはりその時代にやってみたい、というところはあった。それが一番大きい理由です。
(*)大阪万国博覧会EXPO'70にて松本俊夫は「せんい館」の総合プロデュースを担当する。
横尾忠則の他、秋山邦晴、今井直次、湯浅譲二、吉村益信、四谷シモンなどが参加。松本は「スペース・プロジェクション・アコ」を出品。
質問:そのプランが実現できるから出品したのでしょうか。西洋近代のパラダイムを問うという意味では前年の69年の京大をピークにして反万博という形で動いていた人達もいたわけですよね。
松本: それはプラス・マイナスいろんな相反する要因を孕んでいて、とても悩みました。政治的な要因でいえば万博というのはやはり国家と結びついているし、もちろ ん国家的なイベントというものの本質を見ていなかったのではないわけで、それはすごく悩んだところではあります。だけども、結局プラス・マイナスの置き換 えのきかないプラス面をやはりここではどうしてもやっておきたいと思ったのです。
もしもやらなかったら多分、「薔薇の葬列」もできなかった。つまりそういうものが、資金になったのです。「薔薇の葬列」なんかでもATGと監督とが半々出 し合って作ったものがATGのアート・シアターのようなものでした。僕も若くて本当に貧乏だったので、そういう資金をつくることも出来なかったのです。簡 単に言えば、万博をやることの中でのギャランティーを、今度はアート・シアターで作る作品の資金源にするといったようなことで、それをまた可能にしてい く。それがさらに次の可能性へと繋がっているというふうに考えれば、やった場合とやらない場合でやっぱりずいぶん違っただろうと。やらなかったら僕の創作 活動はどうなっていたか、恐らくまるで違うものだったと思います。
そういうこともあって、結局は片方を選択しているわけだから、もう片方との関係でどうなったかというのは想像する以外にないですね。
質問:松本さんの作品を通じて、これからの社会を予見したいというような意思を感じました。
松本: 近代というものの行き詰りというものをすごくやっぱり60年代後半から感じるようになって、大げさに言えば人類の文化のありかたに係わるわけです。長い時 間、僕らのライフスタイル、ものの考え方、感じ方、それから価値観、いろんなものを一つの枠組みとして作っているその中でその枠組みの息苦しさをなんとか 変えなきゃいけない。もちろん近代というのは馬鹿にできないわけで、ものすごく大きい足跡を人類の文化に残しているし、ものすごく大きな問題提起もあった し、簡単に否定できるようなものではありませんが、少なくともやっぱり60年代の後半になってくるとその行き詰まりが、いろんな形で出始めていたことは事 実です。
その時代には、近視眼的にいうと70年安保があっただけに、70年安保が決戦であるといったような考え方にみんながなりがちでしたが、―僕はそれも軽視す るわけではないけれども―、僕はもっと射程を大きく捕らえるというか、70年安保といったような射程ではなくて、近代というものをどう超えていくかという ことを、創作の中にあるいは芸術思想の中に孕んでないようでは駄目だと思っています。その追求みたいなものが基調音になっているというのかな、そういう意 味では作家っていうのはみんな少しずつ共通した点もあれば違う面もありますね。
近代の超克と構造主義的アプローチ
質問:超克の仕方というのはどういうことなのでしょうか?
松本:それを一口でいうのは難しいですね、大問題ですから。だからそれは恐らく僕自身は、さっき半世紀って笑い話に出ましたが、実際半世紀かかっているわけで、未だ追求中です。でも時代としてかなり、みんなそういうことを考えるようになってきたのは事実ですね。
質問: 80年代の作品「シフト」はエフェクトを多様されているのですが、それほど難しいエフェクトではないのですが、構成自体が面白くユーモアがあると思いまし た。これは構造主義として捕らえることができると思いますが、シンプルなエフェクトを使っている「シフト」についてのお考えをお願いします。
松本:「シフト」はある意味では追求したことが、よく見える作品かと思います。画面をいつも層にスライスしていますよね。実際の被写体は建物の空間だけで、何も動いているものが一つもないわけです、人も出てこないし。
 「リレーション 関係」(1982)
「リレーション 関係」(1982)撮ったときの素材として動いているのはカメラだけなのです。それを素材にしながら、6層に層をスライスして、その層のお互いのそれぞれのイメージの関係を 時間的にずらしていっているわけです。例えばカメラがずぅーっとパンをした、そうすると上から一段おきに1、2、3、それから戻って4、5、6、というふ うに何分の一秒かをずらして、次々にパンが始まると。そうすると時間のズレが相当な空間の歪みを作っていくわけです。空間のネジレみたいなものを作ってい く。その時間と空間の関係に目を向けているわけですね。
要するに、時間のずれが空間の歪みを作りながら、空間のイメージ全体が思ってもないようなものに変わっていく。あるいは、建物というイメージ自体が最初 の本当の建物はどんな建物だったのだろうとわからなくなるくらい複雑に変容していきますよね。その在り方が、その6つの要素の時間のずれの組み換えをやっ ているわけです。組み換えをやることでイメージがガラっと変わっていく。これは僕が勝手にそう思っているのかも知れませんが、この組み換えというのは、言 語学者ソシュールの晩年の「アナグラムの研究」というのがあり、-アナグラムの研究というのは詩的言語の研究ですが-それで言葉の置き換えをやるわけで す。アナグラムというのは、西洋のアルファベットを扱う言葉の人達は、単語などを一つ一つ切り離して、それを置き換えるわけですね。すると全然別の意味の 単語に変わってしまったりする。そういう遊びがあって、ゴダールなんかはしきりにそのアナグラムを映画の中に持ち込んでいます。
それを単語の個々の単語の単位じゃなくて、もうちょっとイメージの単位で置き換えをやっていったときに、これはイメージがアナグラムみたいに、若干似た関 係で生まれてくる。そのアナグラムの在り方の中に、時空間の解体と再構成といったようなことが生まれて、ものを生み出していくときの原理がそこに体現して ゆき、それが構造的であると、こだわっていたのです。構造そのものというよりは構造化なのです。構造化というプロセスとそのメカニズムそのものを見ていく というような作品だったのです。
それで、建物はある意味では仮の素材としてそういうものが現れやすい建物を選んだということなのですが、偶然かどうか分からないけれどこの年にたまたま 日本建築学会100年記念の学会が開かれて、その学会の大会でこれを上映させてくれと言ってきたのです。
建物自体は別に建築学会で今、大騒ぎするような建物ではないわけで、何を考えているのかと思ったのですが、後で聞いてみると、やはり建築の設計原理とし ていろんな建築上の要素、構造的な要素の単位をいろんな形で組み替えていると。
ユニットとしての構造の組み替えを通して、建築の設計をどんどん展開していくといったような発想を刺激するのでお借りしたんだということで、やっぱり共通しているなと思いました。
瀬島:建築学会100周年のときの相談がきたときに映像で何か、建築学会と映像の接点で何かイベントをやりたいという相談がありました。それで、どういう作品がいいのか、インスタレーションにするのがいいのか。
松本:82年ですね、これは。
瀬島: そこで、いろいろ考え、私としてはこの「シフト」がぴったりではないかなと思いました。たまたまこの建築学会が大成建設の銀座のビルかどこかでやっていた だいたのですが、この構造がみえてくる映像作品「シフト」と、もう一方にモニターを置いてアメリカのビル群をダイナマイトで爆破して壊していくっていう景 色が延々と流され、それと時折磯崎新さんがレクチャーしている映像との、全部で3つの映像を並べ、ある種一つ一つの構造が組み上がっていくことをやりまし た。インスタレーションとしてはそんなに思ったようなことは出来なかったのですが、やっぱりこの「シフト」という作品がある意味でその頃のデコンストラク ションをかなり考えていた建築家たちには非常に好意を持って見てもらえ、かなりの建築家たちに見て頂いたと思いますね。
松本:それと偶然の一致なんだけれど も、国際建築学会っていうのがボルドー辺りにあって、そこからも言ってきて、それはパリのポンピドゥー・センターでのビデオアートのプログラムがあって、 そこで作品を見た人が「あれを貸してほしい」と言ってきたことがありました。日本の建築学会に言われてそうなったのか、僕は知りませんけれどもそういう意 味では偶然に半年ぐらいの時間差をおいて、そういうことがありましたね。
それからもう一つ、ちょっといわゆるエフェクトをかなり使っているっていうのは、確かにこういう処理っていうのはデジタルな編集システムが初めて入ってき た頃で、-80年代の頭ですから、まだたいしたことは出来ないのですが-そういう試みも含めて、ある段階までは僕はテクノロジーがもたらす芸術方面の可能 性っていうことを、いつも割と大きい要因としてあったのです。
しかし、その後にものすごくそういう装置が増えましてエフェクターみたいなのが増えて猫も杓子も、そういうエフェクトシンドロームみたいな状態が出てきま した。それが逆にすごくそれぞれの作家の固有なこだわり方を曖昧にさせてしまって、似たり寄ったりになってしまいました。
ということがとても気になって、僕は80年代の半ばになると、逆にそういうエフェクトを含めて、幻視的な特殊技術みたいなものをできるだけ使わないという 方向に切り替えて、それが良いというのではなくて、要するに日本全体で起きている流れに一つの疑問を提起するというところがありました。
それからまた、その頃に課題として、-今言ったような時空間のねじれみたいな脱構築みたいな話がでましたけれども-デコンストラクションをもうちょっと人 間がものを意味づけるときの在り方を物語性として捉えると物語の次元ですごく型にはまったようにしか物を見ていない、意味付けをしていない、その辺りの問 題に踏み込んでいく、そこを脱構築する、という方向に向かってですね、意味をぐらつかせるっていう文脈の脱構築の方向に焦点を変えていったのですね。
それは、88年には劇映画で「ドグラマグラ」という作品を作りました。ご覧になった方は、あるいは「ああなるほどそういうつながりでか」とお分かりになる かと思いますが、そういう展開がそのあたりでは、80年代の後半には別な展開へと変わっていってるわけですね。
司会:本日はどうもありがとうございました。
参考資料:「ビデオ・新たな世界-そのメディアの可能性」カタログ(O美術館/1992)/「'75松本俊夫映像個展」カタログ(アンダー・グラウンド・センター)/「光と風の庭カタログ」(愛知万博瀬戸日本館)/キノバラージュ松本俊夫特集
その1へ
---------------------------------------
2001年から2005年のファイドロス・カフェのビデオアート・ショーイングは今回が最終回となり、カフェも4月に閉店することになっており、上映会終了後、瀬島久美子さんからカフェのオーナーの戸田久美子さんに花束が渡されました。
2001年に若手ビデオ作家の邂逅の場として、また一般のお客に気軽に映像作品を見てもらおうというアイデアから戸田久美子さんとビデオアーティスト河合 政之氏がオープンしたファイドロス・カフェでしたが、3年間様々なゲストやアーティストを迎えて渋谷に一つの映像文化の拠点を作り上げました。この松本俊 夫さんと瀬島久美子さんのゲストを迎えてのファイドロス・カフェのビデオアート・ショーイングが最終回となりました。3年間本当にありがとうございまし た。